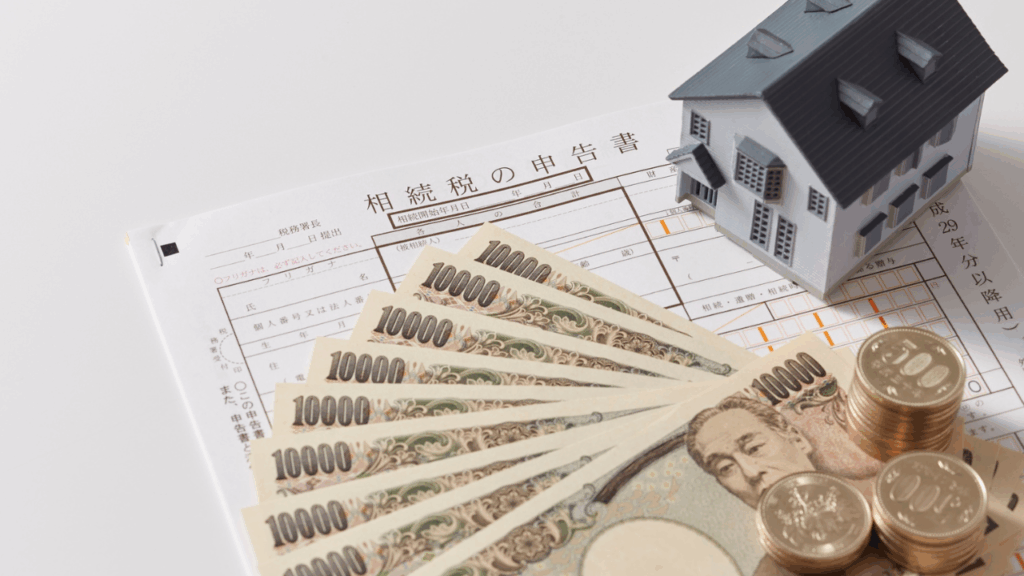
相続と3,000万円特別控除|相続税と不動産売却の2つの制度を徹底比較
相続が発生した際、「3,000万円の控除」という言葉を耳にする機会は多いのではないでしょうか。実は、相続に関連する3,000万円の控除には、大きく分けて2つの制度が存在します。それが「相続税の基礎控除」と「相続した空き家を売却する際の特別控除」です。
この2つの制度を正しく理解しておかないと、数百万円単位で税金の負担が変わってしまう可能性があります。特に、親から相続した実家を売却する予定がある方は、どちらの制度が使えるのか、しっかり確認しておく必要があります。
本記事では、相続における3,000万円控除について、以下のポイントを中心にわかりやすく解説します。
- 相続税の基礎控除と相続空き家売却時の特別控除の違い
- それぞれの制度の適用要件と計算方法
- 確定申告の手続きと必要書類
- 他の特例との併用可否
- 具体的な節税シミュレーション
相続した不動産の扱いで迷っている方は、ぜひ最後まで読んで、最適な節税方法を見つけてください。
相続における3,000万円特別控除とは?2つの制度の違いを理解しよう
親が亡くなって相続が発生すると、「3,000万円の控除が使える」という話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。実は、この「3,000万円控除」には2つの全く異なる制度があるんです。この違いを知らずに手続きを進めてしまうと、本来払わなくていい税金を何百万円も払ってしまう可能性があります。
1つ目は「相続税の基礎控除」で、亡くなった方の財産全体に対して適用されるものです。これは相続が発生したら自動的に使える控除で、特に申請の必要はありません。2つ目は「被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除」で、相続した実家などを売却する際に使える制度です。こちらは確定申告が必要になります。
たとえるなら、前者は「相続という試合に参加するだけでもらえるボーナス」で、後者は「相続した家を売却したときにもらえる追加のボーナス」というイメージです。どちらも節税効果は絶大ですが、使える場面やタイミングがまったく違います。ここからは、それぞれの制度について詳しく見ていきましょう。
相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)
相続税の基礎控除は、相続が発生したときに誰でも使える最も基本的な控除制度です。「基礎控除」という名前の通り、この金額までは相続税が一切かからない、いわば「非課税枠」のようなものなんです。
計算式はとてもシンプルで、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となります。たとえば、お父さんが亡くなって、相続人がお母さんと子ども2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」になります。つまり、相続財産の総額が4,800万円以下であれば、相続税は1円もかからないということです。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続財産がこの金額以下なら相続税はゼロ
- 特別な申請や手続きは不要で自動的に適用される
- 相続人の数が多いほど控除額も増える仕組み
この制度のすごいところは、何も手続きをしなくても自動的に適用されることです。相続税の申告が必要かどうかを判断する際の最初の目安になるので、まずはこの基礎控除額を計算してみることをおすすめします。相続財産には、現金や預金だけでなく、不動産や株式、生命保険金なども含まれるので注意が必要です。
被相続人の居住用財産を売却した場合の3,000万円特別控除
もう1つの3,000万円控除は、相続した実家などを売却するときに使える制度で、正式名称を「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」といいます。これは相続税とは全く別の話で、不動産を売却したときに発生する「譲渡所得税」を軽減するための制度なんです。
少し複雑に聞こえるかもしれませんが、要するに「親が一人暮らしをしていた実家を相続して売却したら、その売却益から3,000万円まで差し引けますよ」という制度です。たとえば、相続した実家を5,000万円で売却して、取得費や諸経費を差し引いた利益が3,500万円だったとします。通常ならこの3,500万円に対して約20%の税金(約700万円)がかかりますが、この特別控除を使えば500万円だけが課税対象となり、税額は約100万円で済むのです。
この制度が作られた背景には、全国で増え続ける空き家問題があります。親が亡くなった後、実家を放置してしまう人が多く、それが地域の景観や防犯上の問題を引き起こしています。そこで国は、「早めに売却してもらえば税金を大幅に軽減しますよ」というインセンティブを設けたのです。ただし、この制度を使うには確定申告が必須で、いくつかの厳しい要件もクリアしなければなりません。
- 相続した実家などの売却益から最大3,000万円を控除できる
- 譲渡所得税と住民税の節税効果が非常に大きい
- 確定申告が必須で、要件を満たさないと適用されない
- 空き家問題の解決を目的とした政策的な制度
どちらの制度が自分に当てはまるのか見極めるポイント
ここまで2つの制度を説明してきましたが、「結局、自分はどっちを使えるの?」と混乱している方もいるかもしれません。安心してください。実は、この2つの制度は使うタイミングも目的も全く違うので、両方使える可能性もあるんです。
まず「相続税の基礎控除」は、相続が発生した時点で自動的に適用されます。相続財産がこの基礎控除額を超えている場合にのみ、相続税の申告が必要になります。一方、「被相続人の居住用財産の特別控除」は、相続した不動産を実際に売却したときに初めて使える制度です。つまり、相続税を払った後でも、さらに実家を売却する際に使えるということなんです。
- 相続税の基礎控除:相続発生時に自動適用される(申告不要の場合あり)
- 居住用財産の特別控除:相続した実家を売却する際に使える(確定申告必須)
- 2つの制度は別々に適用されるため、併用も可能
- 相続税を払った人でも、売却時の控除は使える
見極めのポイントは、「今どの段階にいるのか」を考えることです。相続が発生したばかりなら、まずは基礎控除を使って相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。そして、相続した実家を売却する予定があるなら、売却時の特別控除が使えるかどうかも同時にチェックしておくと安心です。特に、親が一人暮らしをしていた実家を相続した場合は、この売却時の控除が大きな節税につながる可能性が高いので、絶対に見逃さないようにしましょう。
相続税の基礎控除における3,000万円の役割
相続税の基礎控除は、相続における最初の大きな「壁」であり、同時に「守り」でもあります。この基礎控除があるおかげで、実は日本で相続税を払っている人は全体の約8~9%程度しかいないんです。つまり、10人中9人は相続税を払わなくて済んでいるということ。この3,000万円という金額が、まさに最初の砦として機能しているわけですね。
この基礎控除の仕組みを正しく理解しておけば、「うちは相続税がかかるのか、かからないのか」という最も基本的な疑問に答えることができます。相続が発生すると、ただでさえ葬儀や各種手続きで慌ただしい中、税金の心配まで加わると本当に大変です。でも、基礎控除の計算方法さえ知っていれば、まず最初の不安を取り除くことができるんです。
ここからは、基礎控除の具体的な計算方法や、法定相続人の数え方、そして実際にどんなケースで相続税がかかるのかを詳しく見ていきましょう。専門用語も出てきますが、一つひとつ丁寧に説明していきますので、安心してついてきてくださいね。
基礎控除の計算方法と具体例
基礎控除の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と非常にシンプルです。この600万円という数字が、相続人一人あたりに加算される金額なんです。たとえるなら、3,000万円という基本料金に、相続人の数だけ追加のクッションが増えていくイメージですね。
具体例を見てみましょう。お父さんが亡くなり、相続人がお母さん、長男、長女の3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。もし相続財産の総額が4,500万円だったら、基礎控除額の4,800万円を下回っているので、相続税は一切かかりません。逆に、相続財産が6,000万円だったら、6,000万円-4,800万円=1,200万円が課税対象となり、この金額に対して相続税が計算されることになります。
- 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 相続人が1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円
- 相続財産の総額が基礎控除額以下なら相続税はゼロ
- 超えた部分だけが課税対象になる
もう一つ例を挙げると、お母さんが亡くなって相続人が子ども4人だけの場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×4人=5,400万円」になります。このように、相続人の数が増えれば増えるほど、非課税枠も大きくなっていくんです。ただし、相続財産には預金だけでなく、不動産の評価額、株式、生命保険金(一定額を超えた部分)、死亡退職金(一定額を超えた部分)なども含まれるので、意外と総額が大きくなることがあります。特に不動産は評価額が高額になりやすいので注意が必要です。
法定相続人の数え方と注意点
基礎控除を正しく計算するには、「法定相続人」の数を正確に把握することが絶対に必要です。法定相続人とは、民法で定められた「相続する権利を持つ人」のことで、この人数によって基礎控除額が大きく変わってきます。
法定相続人には優先順位があります。まず配偶者は必ず相続人になります。そして、第1順位が子ども(亡くなっている場合は孫)、第2順位が親(直系尊属)、第3順位が兄弟姉妹です。たとえば、亡くなった方に配偶者と子どもがいる場合、法定相続人は配偶者と子どもだけで、親や兄弟姉妹は相続人にはなりません。子どもがいなければ配偶者と親、子どもも親もいなければ配偶者と兄弟姉妹が相続人になるという仕組みです。
- 配偶者は常に法定相続人になる
- 第1順位:子ども(代襲相続で孫も含む)
- 第2順位:親や祖父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続で甥姪も含む)
- 上位の順位がいれば下位の順位は相続人にならない
ここで注意したいのが、「相続放棄をした人」の扱いです。相続放棄をした人は、最初から相続人ではなかったものとして扱われます。つまり、相続人が3人いて1人が相続放棄した場合、基礎控除の計算では「相続人2人」として計算するのです。また、養子がいる場合は実子と同じく法定相続人にカウントされますが、税務上は実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしか基礎控除の計算に含められないというルールがあります。これは、養子を増やして基礎控除額を増やす節税策を防ぐための規定なんです。
相続税がかからないケースとかかるケース
「うちは相続税がかかるのだろうか」という不安は、相続を迎える多くの家庭が抱える共通の悩みです。実際のところ、先ほども触れたように、日本全体では約91~92%の方が相続税を払わずに済んでいます。これは基礎控除のおかげなんですね。
相続税がかからない典型的なケースを見てみましょう。たとえば、お父さんが亡くなり、相続財産が自宅(評価額2,500万円)と預金1,500万円の合計4,000万円、相続人がお母さんと子ども2人の3人だった場合。基礎控除額は4,800万円ですから、相続財産4,000万円は基礎控除の範囲内に収まり、相続税は一切かかりません。このようなケースでは、そもそも相続税の申告自体が不要なんです。
一方、相続税がかかるケースはどうでしょうか。同じく相続人が3人で、相続財産が自宅(評価額4,000万円)、預金2,000万円、株式1,500万円の合計7,500万円だった場合。基礎控除額は4,800万円ですから、7,500万円-4,800万円=2,700万円が課税対象となり、この金額に対して相続税が計算されます。この場合は、相続税の申告と納税が必要になります。
- 相続財産が基礎控除額以下なら相続税はゼロ(申告も不要)
- 都市部で不動産を持っている場合は注意が必要
- 生命保険金や死亡退職金にも非課税枠がある(500万円×法定相続人の数)
- 小規模宅地等の特例を使えば自宅の評価額を最大80%減額できる場合も
特に注意が必要なのは、都市部に不動産を持っている場合です。東京や大阪などの大都市では、小さな一戸建てでも評価額が3,000万円を超えることは珍しくありません。預金や株式などの金融資産が少なくても、不動産だけで基礎控除額を超えてしまうケースがあるのです。ただし、「小規模宅地等の特例」という制度を使えば、居住用の宅地の評価額を最大80%減額できる可能性もあります。この特例を使えば、評価額4,000万円の自宅が800万円になり、結果的に相続税がかからなくなることもあるんです。相続税の判断は、こうした特例も含めて総合的に考える必要があるため、心配な場合は早めに税理士に相談することをおすすめします。
相続した空き家を売却する際の3,000万円特別控除
親が一人暮らしをしていた実家を相続したものの、誰も住む予定がなく、どうしようか迷っている方は少なくありません。そのまま放置すれば固定資産税はかかり続けますし、建物も傷んでいく一方です。かといって売却すると、利益が出た場合には高額な譲渡所得税がかかってしまう…。そんなジレンマを抱えている方に朗報なのが、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」です。
この制度を使えば、相続した実家を売却したときの利益から最大3,000万円を差し引くことができます。譲渡所得税は通常、利益に対して約20%もの税率がかかるため、3,000万円控除できるということは、最大で600万円もの税金が軽減されるということです。これは本当に大きな金額ですよね。
ただし、この制度には細かい要件がたくさんあり、知らずに売却を進めてしまうと控除が使えなくなってしまう可能性もあります。ここからは、この制度の詳しい内容と、どんな点に注意すべきかを丁寧に解説していきます。親から相続した実家の扱いで悩んでいる方は、ぜひ最後まで読んでみてください。
被相続人居住用財産の3,000万円特別控除とは
「被相続人居住用財産に係る譲渡所得の特別控除」、正式名称は長くて覚えにくいですが、一般的には「空き家の3,000万円控除」や「相続空き家の特別控除」と呼ばれています。この制度は、親が一人で住んでいた家を相続し、その後売却した場合に、売却益から最大3,000万円を控除できるという制度です。
たとえば、お父さんが一人暮らしをしていた実家を相続し、4,000万円で売却したとします。この家を建てたときの費用(取得費)や売却にかかった仲介手数料などの経費が合計1,000万円だったとすると、譲渡所得は3,000万円になります。通常なら、この3,000万円に対して約20%、つまり600万円もの税金がかかってしまいます。しかし、この特別控除を使えば、3,000万円全額が控除されて課税対象はゼロになり、税金も一切かからないのです。
- 相続した実家の売却益から最大3,000万円を控除できる
- 通常の譲渡所得税率は約20%なので、最大600万円の節税効果
- 被相続人が一人暮らしをしていた家が対象
- 相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要がある
この制度の素晴らしい点は、マイホームの3,000万円控除と同じ控除額が使えることです。通常、マイホームの特別控除は「自分が住んでいた家」を売却した場合にしか使えませんが、この相続空き家の特別控除を使えば、親が住んでいた家でも同じように大きな控除が受けられるんです。ただし、適用には厳しい要件があり、その要件を満たさないと控除は使えません。次の章で詳しく見ていきますが、特に「売却のタイミング」と「家の状態」には十分な注意が必要です。
制度創設の背景と目的
この「被相続人居住用財産の特別控除」は、平成28年(2016年)の税制改正で新しく作られた比較的新しい制度です。なぜこの制度が作られたのか、その背景を知ると、制度の趣旨がよく理解できます。
日本では少子高齢化が進み、親世代が亡くなった後、子ども世代は既に自分の家を持っているため実家に戻らない、というケースが急増しています。その結果、誰も住まない空き家が全国で増え続け、令和5年時点で全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%にも達しています。空き家が増えると、建物の老朽化による倒壊リスク、不審者の侵入、雑草や害虫の発生、景観の悪化など、さまざまな社会問題を引き起こすのです。
国としては、この空き家問題を何とか解決したい。でも、相続した実家を売却すると高額な税金がかかるとなれば、なかなか売却に踏み切れない人も多いはずです。そこで、「早めに売却してくれれば、税金を大幅に軽減しますよ」というインセンティブを設けたのが、この制度なんです。まさに、空き家を減らすための政策的な誘導策というわけですね。
- 全国の空き家は約900万戸、空き家率は13.8%(令和5年時点)
- 相続した実家が放置されることによる社会問題が深刻化
- 早期売却を促進するための税制上のインセンティブ
- 平成28年度税制改正で創設、令和5年度まで延長されている
この制度には期限があり、当初は令和5年12月31日までの売却が対象でしたが、その後延長され、現在は令和9年12月31日までの売却が対象となっています。つまり、今相続した実家をどうしようか悩んでいる方にとっては、まさに活用すべきタイミングなんです。ただし、制度の期限は政治や経済状況によって変わる可能性があるため、売却を検討しているなら早めに動いた方が安心です。また、この制度を使うには、単に「古い家を売る」だけではなく、耐震基準を満たしているかどうかなど、クリアすべき条件がいくつもあります。
通常のマイホーム売却時の3,000万円控除との違い
「3,000万円控除」という言葉を聞くと、「あれ、マイホームを売るときにも3,000万円控除があったような…」と思った方もいるかもしれません。その通りです!実は、自分が住んでいた家を売却するときに使える「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除」という制度も存在します。この2つの制度は名前も控除額も似ていますが、適用される対象が全く違うんです。
通常のマイホーム売却時の3,000万円控除は、「自分が住んでいた家」または「住まなくなってから3年以内の家」を売却した場合に使える制度です。つまり、あなた自身が実際に住んでいたことが条件になります。一方、相続空き家の3,000万円控除は、「親が一人で住んでいた家を相続した後に売却する」場合に使える制度です。自分が住んでいなくても使えるというのが大きな違いですね。
- マイホーム売却の控除:自分が住んでいた家が対象
- 相続空き家の控除:親が一人で住んでいた家を相続後に売却する場合が対象
- どちらも控除額は最大3,000万円で同じ
- 2つの制度を同時に使うことはできない
- 相続空き家の控除には「昭和56年5月31日以前に建築」などの追加要件がある
たとえば、あなたが結婚して実家を出て、その後お父さんが亡くなって実家を相続したとします。あなた自身は実家に住んでいなかったので、通常のマイホーム控除は使えません。でも、お父さんが一人暮らしをしていた家なら、相続空き家の控除が使える可能性があるんです。逆に、お父さんとお母さんが二人で暮らしていた家なら、相続空き家の控除は使えません(被相続人が一人暮らしという条件を満たさないため)。ただし、お母さんが老人ホームに入居していた場合など、例外的に認められるケースもあります。このように、2つの制度は似ているようで適用される場面が全く違うので、自分のケースがどちらに当てはまるのか、慎重に見極める必要があります。
相続空き家の3,000万円特別控除の適用要件
相続空き家の3,000万円特別控除は、非常に節税効果の高い制度ですが、その分適用要件も厳しく設定されています。この要件を一つでも満たさないと、控除は使えなくなってしまいます。「知らなかった」「うっかり見落としていた」では済まされない、数百万円単位の損失につながる可能性があるのです。
ここからは、適用要件を「被相続人に関する要件」「家屋に関する要件」「売却時期に関する要件」「耐震基準」「売却価格」の5つに分けて、一つひとつ詳しく見ていきます。専門用語も出てきますが、できるだけわかりやすく説明していきますので、該当しそうな方はメモを取りながら読み進めてください。特に、売却を検討している段階の方は、要件を満たすために今できることもあるはずです。
被相続人に関する要件
まず最初に確認すべきは、亡くなった方(被相続人)に関する要件です。この制度は、親が「一人暮らし」をしていた家を相続した場合に限定されているという点が最も重要なポイントになります。
具体的には、被相続人が相続開始の直前まで、その家に「一人で」住んでいたことが条件です。たとえば、お父さんが一人暮らしをしていた実家を相続したケースなら、この要件を満たします。しかし、お父さんとお母さんが二人で暮らしていて、お父さんが亡くなった場合は、お母さんがまだ生きているため「一人暮らし」の要件を満たさず、控除は使えません。この場合は、お母さんが亡くなった後であれば、要件を満たす可能性があります。
- 被相続人が相続開始直前まで一人で住んでいたこと
- 配偶者や他の同居者がいた場合は原則として対象外
- 要介護認定を受けて老人ホーム等に入居していた場合は例外的に認められる
- 被相続人以外に同居していた相続人がいないこと
ただし、「一人暮らし」の要件には重要な例外があります。それが「老人ホーム等への入居」です。被相続人が要介護認定や要支援認定を受けて、老人ホームや介護施設に入居していた場合、その施設に入居する直前まで一人で住んでいたのであれば、この制度の対象になる可能性があります。この場合、被相続人住民票の除票や介護保険の認定証明書などで、老人ホームに入居していたことや、その前に一人暮らしをしていたことを証明する必要があります。高齢化が進む現代では、このような例外規定は非常に重要で、多くの方に関係してくるポイントです。
家屋に関する要件
次に確認すべきは、相続した家そのものに関する要件です。この制度は、どんな家でも対象になるわけではなく、主に「古い一戸建て住宅」を対象としています。なぜなら、この制度の目的が「老朽化した空き家を減らすこと」にあるからです。
まず、家屋は昭和56年5月31日以前に建築されたものでなければなりません。これは、現行の耐震基準(新耐震基準)が昭和56年6月1日に施行されたことに関係しています。つまり、旧耐震基準で建てられた、比較的古い建物が対象ということです。また、建物の構造は「区分所有建物登記がされていないこと」が条件となっており、これは簡単に言えば「マンションは対象外」ということを意味します。基本的には一戸建ての家が対象なんです。
さらに、被相続人が「その家を居住の用に供していた」ことも要件です。つまり、単に所有していただけではダメで、実際に住んでいた家でなければなりません。たとえば、被相続人が別荘として使っていた家や、賃貸に出していた家は対象外になります。また、相続開始から売却までの間、その家や土地を「事業の用、貸付けの用または居住の用に供していないこと」も条件です。相続後に誰かが住んだり、賃貸に出したりすると、控除が使えなくなってしまうので注意が必要です。
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること(旧耐震基準)
- 区分所有建物登記がされていないこと(マンション等は対象外)
- 被相続人が実際に居住していた家であること
- 相続から売却まで、空き家のままで、賃貸や居住に使っていないこと
売却時期に関する要件
この制度には「いつまでに売却しなければならないか」という期限が設けられています。この期限を過ぎてしまうと、他の要件をすべて満たしていても控除は使えなくなってしまうので、非常に重要なポイントです。
具体的には、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却することが条件です。少し複雑な表現ですが、例を挙げて説明しましょう。たとえば、お父さんが令和4年(2022年)7月15日に亡くなったとします。「3年を経過する日」は令和7年(2025年)7月15日ですが、「その日の属する年の12月31日」なので、令和7年12月31日までに売却すればOKということです。つまり、実質的には3年半ほどの猶予があるわけですね。
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却
- 売却期限は「契約締結日」ではなく「引渡日」で判断
- この制度自体の適用期限は令和9年12月31日まで
- 両方の期限を満たす必要がある
ここで注意したいのは、「売却」のタイミングです。税法上、不動産の売却は「引渡しの日」を基準に判断されます。契約を結んだ日ではありません。たとえば、令和7年12月15日に売買契約を結んでも、引渡しが令和8年1月15日になってしまったら、期限を過ぎてしまうのです。年末近くに売却を考えている場合は、引渡し日が年内に確実に完了するように、余裕を持ったスケジュールを組むことが大切です。また、この制度自体にも適用期限があり、令和9年12月31日までの売却が対象となっています。つまり、相続からの期限と制度自体の期限、両方を満たす必要があるということを覚えておきましょう。
耐震基準を満たすための条件
相続空き家の3,000万円控除を受けるためには、売却時点で「現行の耐震基準を満たしている」ことが必須条件です。この要件が、実は多くの方にとって最も高いハードルになっています。なぜなら、旧耐震基準で建てられた古い家のほとんどは、現行の耐震基準を満たしていないからです。
耐震基準を満たすための方法は、主に2つあります。1つ目は「耐震リフォームを行う」方法。これは、家の柱や壁を補強して、現行の耐震基準を満たすように改修する方法です。ただし、耐震リフォームには数百万円単位の費用がかかることが多く、古い家の場合はリフォームしても思ったほど強度が上がらないケースもあります。そのため、費用対効果をよく考える必要があります。
2つ目は「家屋を取り壊して更地にする」方法です。実は、この方法が最も一般的に使われています。家屋を取り壊して土地だけを売却する場合でも、この特別控除は適用されるのです。取り壊し費用は100万円~200万円程度かかりますが、耐震リフォームに比べれば安く済むことが多く、更地にした方が買い手も見つかりやすいというメリットもあります。
- 売却時点で現行の耐震基準を満たしている必要がある
- 方法①:耐震リフォームを実施して基準を満たす
- 方法②:家屋を取り壊して更地にする
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写しが必要
- 取り壊しの場合は更地の状態で売却すること
どちらの方法を選ぶかは、家の状態や立地、予算などを総合的に考えて判断することになります。たとえば、リフォーム費用が500万円かかる場合と、取り壊し費用が150万円の場合なら、取り壊しを選ぶ方が経済的です。ただし、家屋に歴史的価値がある場合や、立地が良くてリフォーム後に高く売れる見込みがある場合は、リフォームを選ぶメリットもあります。いずれにせよ、耐震基準を満たしたことを証明する書類(耐震基準適合証明書など)を取得する必要があるので、専門家に依頼して適切な手続きを踏むことが重要です。
売却価格の上限
相続空き家の3,000万円特別控除には、実は「売却価格の上限」という重要な条件があります。この条件を知らずに高値で売却してしまうと、控除が使えなくなってしまうので要注意です。
具体的には、売却価格が1億円を超える場合、この特別控除は適用されません。たとえば、都市部の一等地にある実家を相続し、1億2,000万円で売却できたとしても、1億円を超えているため3,000万円控除は使えないのです。この場合、通常の譲渡所得税が満額かかってしまいます。
- 売却価格が1億円以下であること
- 1億円を超えた場合は控除の適用なし
- 土地と建物を合わせた総額で判断
- 複数の相続人で分けて売却した場合も合計額で判断
ここで注意したいのは、「複数の相続人で共有している場合」の扱いです。たとえば、兄弟3人で相続した実家を、それぞれの持分に応じて売却した場合でも、売却価格は合計額で判断されます。一人あたりの受取額が3,500万円ずつで合計1億500万円になったら、全員が控除を使えなくなってしまうのです。ただし、3,000万円の控除額自体は各相続人がそれぞれ使えるため、売却価格が1億円以下であれば、相続人が多いほど有利になります。たとえば、兄弟3人で相続した場合、理論上は3人合わせて9,000万円まで控除できることになります。売却価格の交渉をする際は、この1億円という上限を意識して、ギリギリ超えないように調整することも一つの戦略と言えるでしょう。
相続空き家の3,000万円特別控除が使えないケース
ここまで、相続空き家の3,000万円特別控除を受けるための要件を詳しく見てきましたが、実は「原則として使えないけれど、例外的に使えるケース」や「完全に使えないケース」というものも存在します。これらのケースを事前に知っておかないと、売却を進めてしまってから「実は控除が使えなかった」と気づいて後悔することになりかねません。
特に、老人ホームに入居していた場合や、複数人で相続した場合、親族に売却した場合など、実際によくあるシチュエーションでの取り扱いは、多くの方が疑問に思うポイントです。ここからは、そうした「微妙なケース」について、一つひとつ丁寧に解説していきます。自分のケースが当てはまらないか、しっかり確認してください。
老人ホーム入居など被相続人が居住していなかった場合の特例
「被相続人が亡くなる直前に老人ホームに入居していた」というケースは、現代では非常に多く見られます。高齢化が進む中、要介護状態になって施設に入所する方は年々増えており、「親が老人ホームで亡くなった場合、実家の控除は使えないのか?」という疑問を持つ方は少なくありません。
結論から言うと、一定の条件を満たせば控除は使えます。具体的には、被相続人が要介護認定または要支援認定を受けていて、その認定に基づいて老人ホームや介護施設、障害者支援施設などに入所していた場合、その施設に入所する直前まで一人で住んでいたのであれば、控除の対象になるのです。これは平成31年の税制改正で追加された措置で、現実のニーズに応える形で制度が改善されました。
- 要介護認定・要支援認定を受けていた場合は特例が適用される
- 老人ホーム、介護老人保健施設、障害者支援施設などへの入所が対象
- 入所直前まで一人で住んでいたことが条件
- 入所後に他の人が住んでいないことも確認が必要
- 被相続人住民票の除票、介護保険の被保険者証などで証明
たとえば、お父さんが令和2年まで一人で実家に住んでいたが、令和3年に要介護3の認定を受けて特別養護老人ホームに入所し、令和4年に施設で亡くなったとします。この場合、お父さんは入所直前まで一人で実家に住んでいたので、この特例が適用され、実家を売却する際に3,000万円控除が使えます。ただし、証明書類として、介護保険の被保険者証や施設の入所契約書、被相続人の住民票の除票などを確定申告時に提出する必要があります。また、お父さんが施設に入所した後、誰も実家に住んでいないことも条件なので、たとえば息子さんが実家に戻って住んでしまった場合は、控除が使えなくなってしまいます。
共同相続の場合の取り扱い
相続した不動産を複数の相続人で共有している場合、つまり「共同相続」のケースも非常に多く見られます。たとえば、兄弟3人で実家を相続し、それぞれ3分の1ずつの持分を持っているような場合です。このようなケースでは、3,000万円特別控除はどのように適用されるのでしょうか。
結論から言うと、共同相続の場合でも、それぞれの相続人が要件を満たせば、各自が最大3,000万円ずつ控除を受けることができます。つまり、3人で相続した場合、理論上は合計9,000万円まで控除できる計算になります。ただし、売却価格の上限である1億円という条件は全体に対して適用されるため、実際には最大で1億円までの売却益に対して、各人が按分した金額を控除できるということになります。
具体例を見てみましょう。兄弟3人で相続した実家を9,000万円で売却し、取得費や経費を差し引いた譲渡所得が6,000万円だったとします。この場合、各人の譲渡所得は持分に応じて2,000万円ずつになります。そして、各人がそれぞれ2,000万円ずつの控除を受けられるので、結果的に全員が課税対象ゼロとなり、税金はかかりません。
- 共同相続の場合、各相続人がそれぞれ最大3,000万円まで控除可能
- 売却価格1億円の上限は全体に対して適用される
- 各相続人の譲渡所得は持分割合に応じて計算
- 全員が確定申告を行う必要がある
ただし、注意点もあります。共同相続の場合、相続人全員が同じ条件で控除を受けられるわけではありません。たとえば、3人兄弟のうち1人が親と同居していた場合、その人は「被相続人が一人暮らし」という要件を満たさないため、控除が使えません。また、共有者の一人が持分だけを先に売却してしまった場合など、タイミングがずれると全体の控除額に影響が出ることもあります。共同相続の場合は、相続人全員で話し合い、売却のタイミングや方法を統一することが重要です。全員が確定申告を行う必要があるため、書類の準備も共同で進めると効率的でしょう。
特別な関係者への売却は対象外
相続空き家の3,000万円特別控除には、「売却相手」に関する制限もあります。具体的には、配偶者や親子、兄弟姉妹など、「特別の関係がある者」に対して売却した場合は、この控除を受けることができません。
これは、通常のマイホーム売却時の3,000万円控除と同じルールです。なぜこのような制限があるかというと、親族間で形だけの売買を行って税金を逃れようとする行為を防ぐためです。たとえば、相続した実家を弟に形式的に売却し、実際には弟が無償で使い続けるような場合、これは実質的な譲渡とは言えないため、控除の対象外となるのです。
- 配偶者、直系血族、兄弟姉妹への売却は対象外
- 生計を一にする親族への売却も対象外
- 売却後に同族会社に使用させた場合も対象外
- 内縁関係の配偶者なども「特別の関係」に含まれる
「特別の関係がある者」の範囲は、法律上の親族関係だけでなく、実質的な関係も含まれます。たとえば、籍は入れていないけれど事実上の夫婦として生活している内縁関係の相手や、売却後にその不動産を特別な関係者の会社に使わせる場合なども、対象外となる可能性があります。また、形式上は第三者に売却したように見えても、実際には親族が背後にいるようなケースでは、税務署の調査で否認される可能性があります。税務署は、売却の実態を重視して判断するため、書類上だけ取り繕っても意味がありません。相続した実家をどうしても親族に引き継ぎたい場合は、控除をあきらめて通常の譲渡所得税を払うか、あるいは贈与という形を検討することになります。いずれにせよ、税理士などの専門家に相談して、適切な方法を選ぶことが大切です。
相続空き家の3,000万円控除を受けるための確定申告
相続空き家の3,000万円特別控除を実際に受けるためには、必ず「確定申告」を行う必要があります。たとえ控除を適用した結果、税額がゼロになる場合でも、申告をしなければこの控除は認められません。これは非常に重要なポイントで、「税金がかからないから申告しなくていい」と勘違いしてしまうと、後で大きな問題になります。
確定申告と聞くと、「難しそう」「面倒くさそう」と感じる方も多いかもしれません。確かに、不動産の譲渡所得に関する申告は、通常の確定申告よりも添付書類が多く、計算も複雑です。しかし、順を追って準備を進めれば、決して不可能なことではありません。
ここからは、確定申告の期限や提出先、必要な書類のリスト、譲渡所得の計算方法、そして取得費が不明な場合の対処法まで、確定申告に関する実務的な情報を詳しく解説していきます。初めて確定申告をする方でも理解できるように、できるだけわかりやすく説明しますので、安心してください。
確定申告の期限と提出先
不動産を売却した翌年の2月16日から3月15日までが、確定申告の期間です。たとえば、令和6年中に実家を売却した場合、令和7年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。この期間を過ぎてしまうと「期限後申告」となり、無申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。
特に3月15日が土日祝日の場合は、その翌平日が期限となりますが、年度末の繁忙期と重なるため、税務署の窓口は非常に混雑します。ギリギリに駆け込むのではなく、2月中旬から準備を始めて、余裕を持って申告することを強くおすすめします。初めての確定申告で不安がある場合は、税理士に依頼するのも一つの方法です。費用は5万円~15万円程度かかりますが、間違いなく申告でき、節税効果を考えれば十分に価値があります。
- 申告期限:売却した翌年の2月16日~3月15日
- 提出先:売却した不動産の所在地を管轄する税務署
- e-Taxによる電子申告も可能
- 期限後申告にはペナルティがある
提出先は、売却した不動産の所在地を管轄する税務署です。たとえば、東京都世田谷区の実家を売却したなら、世田谷税務署に申告します。ただし、e-Tax(電子申告)を利用すれば、自宅からインターネット経由で申告できます。e-Taxを利用するには、マイナンバーカードとICカードリーダー、または「ID・パスワード方式」の事前登録が必要ですが、一度設定してしまえば、わざわざ税務署に行く必要がなくなるので便利です。令和2年以降、新型コロナの影響もあって電子申告が推奨されており、税務署の窓口も以前ほど対面での相談に力を入れていない傾向があります。そのため、e-Taxの利用を検討する価値は十分にあります。
必要書類の準備リスト
確定申告をスムーズに進めるためには、必要な書類を事前にしっかりと準備しておくことが何より重要です。不動産の譲渡所得に関する申告は、通常の確定申告と比べて添付書類が多く、一つでも欠けていると受理されなかったり、後から追加提出を求められたりします。
まず、譲渡所得の内訳書(国税庁のホームページからダウンロード可能)を作成する必要があります。これは、売却価格や取得費、譲渡費用などを詳細に記載する書類で、確定申告書に添付します。次に、売買契約書のコピー。これは売却時と、可能であれば取得時(親が購入した時)の両方が必要です。取得時の契約書がない場合は、後ほど説明する「概算取得費」を使うことになります。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 売買契約書のコピー(売却時・取得時の両方)
- 登記事項証明書(法務局で取得)
- 被相続人居住用家屋等確認書(市区町村の窓口で取得)
- 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
- 相続開始から売却までの経緯がわかる書類(電気・ガスの閉栓証明など)
- 老人ホーム入所の場合は、介護保険の被保険者証や施設の入所契約書
特に重要なのが「被相続人居住用家屋等確認書」です。これは、売却した不動産が相続空き家の要件を満たしていることを、市区町村が確認して発行する書類です。この書類がないと、3,000万円控除は絶対に受けられません。発行には1~2週間程度かかることがあるので、売却が決まったら早めに市区町村の窓口(多くの場合、税務課や都市計画課)に相談しましょう。また、家屋を取り壊した場合は、取り壊し証明書や閉鎖事項証明書(取り壊し後の登記情報)も必要になります。必要書類は自分のケースによって異なるため、確定申告の前に一度税務署や税理士に確認しておくと安心です。
譲渡所得の計算方法
確定申告で最も重要かつ複雑なのが、「譲渡所得」の計算です。譲渡所得とは、簡単に言えば「不動産を売却して得た利益」のことで、この金額に対して税金が課されます。計算式は以下の通りです。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
「売却価格」は、実際に不動産を売った金額です。たとえば、4,500万円で売却したなら、この金額が売却価格になります。「取得費」は、その不動産を取得(購入)したときにかかった費用のことです。親が購入した価格や、購入時の仲介手数料、登記費用などが含まれます。建物の場合は、経年劣化を考慮した「減価償却費」を差し引いた金額になります。「譲渡費用」は、売却にかかった費用で、仲介手数料、測量費、取り壊し費用、印紙代などが含まれます。
- 譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
- 取得費:購入価格 - 減価償却費 + 購入時の諸費用
- 譲渡費用:仲介手数料、測量費、取り壊し費用、印紙代など
- 特別控除:譲渡所得から3,000万円を差し引く
- 課税譲渡所得:譲渡所得 - 特別控除(3,000万円)
具体例で見てみましょう。売却価格が5,000万円、取得費が2,000万円(親が購入した価格から減価償却費を引いた金額)、譲渡費用が200万円だったとします。この場合、譲渡所得は「5,000万円 - (2,000万円 + 200万円)= 2,800万円」となります。ここから3,000万円の特別控除を適用すると、2,800万円 - 3,000万円 = マイナス200万円となり、課税対象はゼロになります。つまり、税金は一切かかりません。もし控除を使わなければ、2,800万円に対して約20%の税率(長期譲渡所得の場合)がかかり、約560万円もの税金を払うことになるところでした。この差は本当に大きいですよね。
取得費が不明な場合の対処法
譲渡所得を計算する際に最も困るのが、「取得費が分からない」というケースです。親が何十年も前に購入した実家の場合、購入時の契約書が見つからなかったり、そもそも購入価格を親から聞いていなかったりすることは珍しくありません。このような場合、どうすればいいのでしょうか。
税法では、取得費が不明な場合に「概算取得費」を使うことが認められています。概算取得費とは、売却価格の5%を取得費とみなす方法です。たとえば、5,000万円で売却した場合、5,000万円×5%=250万円を取得費として計算できます。ただし、この方法は取得費が非常に少なくなってしまうため、譲渡所得が大きくなり、結果として税金も高額になってしまうというデメリットがあります。
- 取得費不明の場合は「概算取得費」を使える(売却価格の5%)
- 概算取得費を使うと譲渡所得が大きくなり税負担が増える
- できる限り実額での取得費を証明する努力をすべき
- 古い通帳、確定申告書、住宅ローンの書類などが手がかりになる
できる限り、実際の取得費を証明する方法を探すべきです。たとえば、親の古い通帳に購入代金の引き落とし記録が残っていないか、住宅ローンを組んでいた場合は金融機関に残高証明書を依頼できないか、不動産会社や司法書士事務所に当時の記録が残っていないか、などを確認してみましょう。また、購入した当時の路線価や公示地価、建築費の統計データなどを使って、合理的な取得費を推定する方法もあります。この方法は税理士の力を借りて行うことが多く、税務署に認めてもらうためには相応の根拠資料を揃える必要がありますが、概算取得費を使うよりも有利になる可能性が高いです。取得費の問題は、税額に数百万円単位の差が出ることもあるため、諦めずに調査することが大切です。
まとめ
ここまで、相続に関する2つの「3,000万円控除」について詳しく解説してきました。最後に、重要なポイントをもう一度整理しておきましょう。
まず、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)は、相続が発生したときに自動的に適用される制度で、相続財産がこの金額以下であれば相続税はかかりません。日本では約9割の方が相続税を払わずに済んでいるのは、この基礎控除のおかげです。
一方、相続空き家の3,000万円特別控除は、親が一人暮らしをしていた実家を相続し、その後売却した場合に使える制度です。売却益から最大3,000万円を控除できるため、最大で600万円もの節税効果があります。ただし、厳しい適用要件があり、特に「昭和56年5月31日以前に建築」「耐震基準を満たす」「相続開始から3年以内に売却」「売却価格が1億円以下」といった条件をクリアする必要があります。
この2つの制度は、使うタイミングも目的も異なるため、状況によっては両方を活用することも可能です。相続税の基礎控除で相続税を払った後でも、実家を売却する際には売却時の控除が使えるのです。
相続は人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、制度を正しく理解し、使える控除は漏れなく活用することが大切です。特に、相続空き家の控除は期限があり、要件も複雑なため、早めに専門家に相談することをおすすめします。税理士費用は数万円~十数万円かかりますが、数百万円の節税効果を考えれば、決して高い投資ではありません。
相続した不動産の扱いで悩んでいる方は、まずは自分のケースがどの制度に当てはまるのかを確認し、必要な手続きを一つひとつ進めていきましょう。正しい知識と適切な準備があれば、相続における税負担を大幅に軽減することができます。この記事が、皆さんの賢い節税の一助となれば幸いです。
